ソフトマター物理への招待
まずは身の回りを見てみよう。あなたがのぞいているディスプレーは液晶が配列して文字や絵を表示しているし、叩いているキーボードのキートップはプラスチックでできている。コンピューターの筐体もプラスチックの場合も多いだろう。手元にあるのはガラスのジョッキに注がれて泡が盛り上がっているビールだろうか?それともコーヒーやお茶だろうか?コーヒーだったらミルクを入れているかもしれない。いずれにせよ飲み終わったら台所に持って行って、洗剤で良く洗うことであろう。手が荒れないようにするためには、ゴム手袋をした方が良いだろう。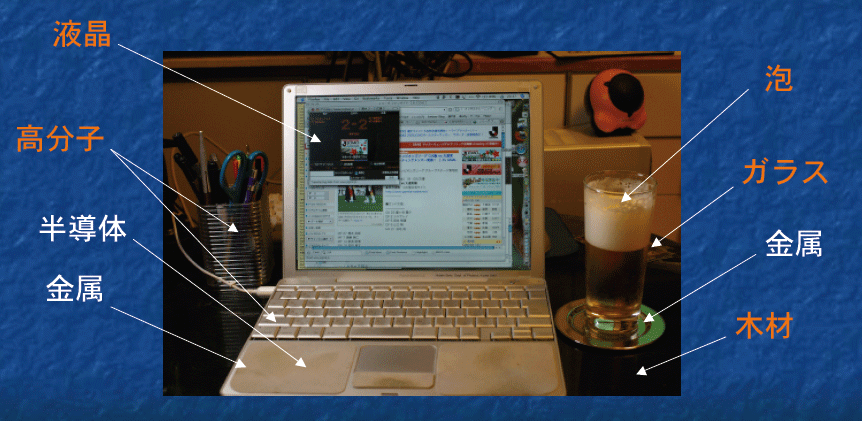
上に書いたのはほんのちょっとした例である。下線を付けた部分が、ここで説明しようとしている「ソフトマター」と言われる物質系の一例なのだ。世の中、家や橋や道路などのしっかりした構造物を作るには、金属やセラミックス等の「ハードマター」を利用した方が良いのは当然だが、それだけでは豊かな生活は営めない。衣類や食事やその他もろもろ、生活を豊かにするために用いられる物質は「ソフトマター」に分類されるものの方が圧倒的に多いのだ。だいたい人間の身体だって、「ハード」なのは骨や歯などほんの一部だけである。その他の器官はほとんど全てが、やわらかな物質でできているのである。
もちろん人間は有史以来これら「ソフトマター」を生活に利用してきた。動物の毛皮を縫って衣服を作ったのは2,3万年前と言われていて、布の発明はもう少し新しいらしいが、いずれにせよ「青銅器時代」は5000年前頃からだと考えられているから、金属と同程度かそれ以上の付き合いがあるのは間違いない。18世紀の産業革命は繊維工業から始まっているし、鉄鋼などの重工業が盛んになった第二次産業革命の頃には高分子が初めて合成されている。すなわち化学や工業の分野では、ソフトマターはハードマターよりも先を進んでいた、と言って良いであろう。
ところが物理学の歴史からみると、状況はむしろ逆なのである。熱機関の振舞いを説明しようと言う動機から熱力学が発展したのは19世紀のこと。統計論を利用することにより多体系を扱う物理学である統計力学が起こったのも、ほぼ同時期の事である。更に20世紀初頭には量子力学の発展が巨大なインパクトを与え、電子の振舞いを記述することにより物質の様々な性質が説明可能であることが分かった。すなわち気体と液体を主に統計力学が、固体を主に量子力学が担当することで、身の回りの物質の性質を説明しようとする物性物理学(あるいは凝縮系の物理学)がスタートすることになる。とりわけ1928年のブロッホによる貢献は大きなもので、彼の理論を出発点とした固体電子論は80年後の今でも物性物理学の主流をなしている、と言って良いのである。
一方、ソフトマターについてはどうか。前述したように高分子や液晶、コロイドなど個別の物質系についての科学には古くから多くの研究者が取り組んでいて、膨大なデータが蓄積され、工業的応用も幅広く行われている。しかしながら物理学的観点から取り組まれるようになったのは、比較的最近の事であると言って間違いない。例えば「ソフトマター」と言う言葉自体が現れたのは、1990年前後のことなのだそうだ。(好村他訳、ハムレー「ソフトマター入門」参照。)また、ソフトマターの物理の研究者として最も著名なド・ジャン(ノーベル賞の受賞者でもある)が高分子物理の本質的な理解に至ったのは、1970年代前半のことらしい。(ド・ジャン「高分子の物理学」参照。)ワトソンとクリックがDNAの二重螺旋構造を明らかにして半世紀が経つが、これを嚆矢として始まった生物物理と比較しても、短い歴史しか持たないのだ。
なぜ、その様な事情になったのか。それはやはり「ソフトマター」自体の難しさにあるのではないか、と思われる。物理学的に見て難しい、と考えられる側面は色々あるが、端的にはその「ソフト」な性質がそうだ。物質が固いか柔らかいかを確かめるには押してみればいいわけだが、これを物理の言葉では「物質の力学的応答を見る」と言う。ある力を加えたときに、少ししか変形しない場合を「固い」と言い、大きく変形するなら「柔らかい」と言うわけだ。少ししか変形しないと言うことは、平衡位置からのずれが小さいと言うこと。すなわち微小変位として扱うことができるわけで、線型応答だけを議論すれば話は済む。だが大きく変形するとなれば話は別だ。最初から非線型応答を扱わなければ、その性質を理解することはできないことになる。
またソフトマターがヘテロな(一様でない、と言うこと)物質系であり、ほとんどの場合中間スケールの構造を持っている、と言うことも事情を複雑にしている要因の一つだ。例えば固体の場合は原子が数Åのスケールで規則正しく並んでいるので、その並んでいる一つの単位(「単位格子」と言われる)の中の電子状態を理解すればマクロな性質も理解できる。(正確には「理解できる場合が多い」と言うべきだが。)すなわち量子力学によるミクロな状態の理解が、マクロな物性の理解に直結する。(一方単純な気体や液体の場合には、統計力学や熱力学が活躍する。こちらは原子や分子の詳細に関わらず、集団としての振舞いを記述できる。)
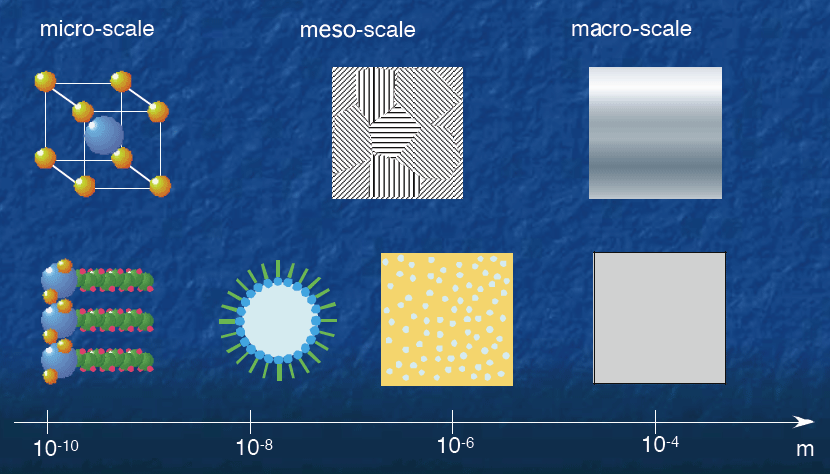
それに対してソフトマターは、多くの場合原子スケールからナノスケール、マクロスケールに至る数層の階層構造を持っている。例えばソフトクリーム(ベタな例だけど)は、氷やタンパク質、油脂、空気等がミリメートル以下のサイズのクラスターをなし、これらが混合していると言う立派な(?)コロイドである。もし分子スケールで混じり合って規則格子を組んでいたりしたら、絶対に滑らかな(ソフトな)舌触りは得られない。
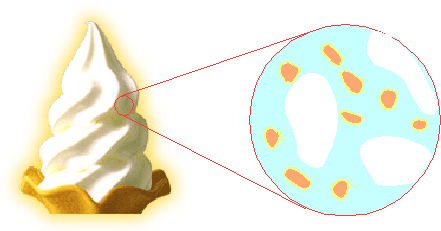
またゼリーやこんにゃく、ゴムなどは全て高分子からできていて、これらが架橋したゲルである。高分子ゲルは一定以上の速さで力を加えると架橋点が動かないため弾性的な性質(固体のような性質)を示すが、ゆっくりした力が加わると架橋点のつなぎ変えが起きて流体のように流れる(こともある)。ゲルに限らず高分子は分子振動や回転、レプテーションなど様々なスケールで様々な特徴的時間の運動モードを持っているので、外力に対する応答も複雑だ。
ついでに言えば、ソフトマターの典型の一つであり、その上最も複雑なのは生命体であろう。例えばタンパク質は巨大な高分子だが、生体内では単純に固まっているわけではなく規則的に折り畳まれた二次構造をなしている。そしてこれらが自発的に自分が居るべき場所(例えば生体膜の特定の部位など)を発見して、その場にいて環境の変化に応じて変形したり化学変化したりしているわけだ。
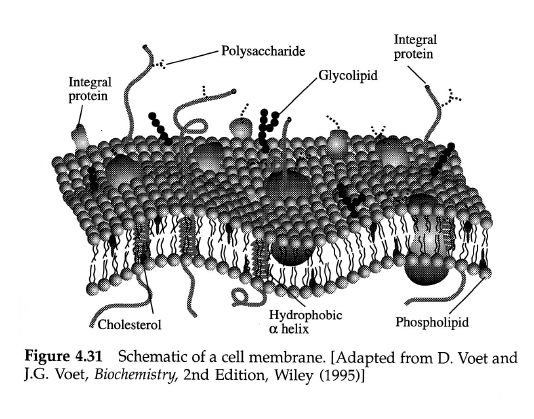
更に生体機能との関連で重要なのはマイクロメータースケールの構造だが、このスケールは熱揺らぎの影響を受けやすい大きさでもある。従って熱の影響を平均化して取り扱うことのできる通常の熱力学や統計力学の環境とは違って、もっとダイレクトに熱(=エネルギー)を扱う必要がある。すなわちこのスケールの世界を正確に理解しようとするならば、非平衡統計力学の枠組みが必要になるのである。
この、少々厄介なソフトマターの世界を物理学で理解しようとするならば、どのような道具立てが必要か。そのためのキーワードは「秩序変数」であり「相転移」であり「自己組織化」であろう。つまり主に固体の振舞いを理解するために用いられて来た統計力学の枠組みを利用して、ナノからミクロ、そしてマクロに至る階層構造を理解することが必要なのだろう、と私は思う。そのためにはまずは平衡論から出発し、階層構造の形成要因を明らかにすると言う流れと、非平衡論からアプローチして物質の性質に具体化していく、と言う両方の流れが必要なのではないだろうか。
ソフトマター物理学(京都大学理学部・理学研究科共通講義「ソフトマター・ソフトマター物理基礎論」講義ノートより)


