NSEの基礎
1.1 中性子散乱とは
1.2 中性子非弾性散乱
2.1 中性子スピンエコーの特徴
2.2 中性子スピンエコーの原理
3.1 NSEの装置
3.2 世界のNSE分光器
4.1 NSEデータの意味
4.2 NSEデータの解析
「中性子スピンエコー法」(Neutron Spin Echo: NSE)は中性子非弾性・準弾性散乱としては最高のエネルギー分解能を誇る方法です。通常の方法(三軸回折計やTOF)のエネルギー分解能は1%程度(10meV程度のエネルギーの中性子を用いて、0.1meVの変化を測定できる)が普通ですが、NSEは10-5ほどの分解能がある、と言われています。どうしてそんなことが可能なのでしょう?
中性子の波長λとエネルギーEの間には、次の関係があります。
E=kBT=(1/2)mv2=h2/(2mλ2)
ここでkBはボルツマン定数、m、vはそれぞれ中性子の質量と速度で、hはプランク定数です。つまり、エネルギーEと波長λは結合していて一方を変えれば他方も変わる関係にあります。従ってEの変化を精密に測定するためには、波長λの分解能を上げなければなりません。
左の図のように元々の中性子(入射中性子、グレーの部分)の波長分布が広い場合には、散乱中性子の中に青い部分のような非弾性散乱があったとしても、弾性散乱を含む散乱中性子全体(赤線の部分)の分布はほとんど変化したようには見えません。そこで非弾性散乱の差が微小な場合には、右の図のように入射中性子の波長分布を絞ってやる必要があります。こうすれば、弾性散乱と非弾性散乱が分離できて高いエネルギー分解能で測定できるのです。
この中性子源における波長分布は、減速材の温度におけるボルツマン分布で決まります。従って入射中性子の波長分解能を上げるためには、中性子を「削る」しかありません。すなわち、エネルギー分解能を上げるためには必然的に中性子強度が落とさざるを得ないのです。従って通常の方法では1%程度(後方散乱などを用いて工夫すれば0.1%程度まで上げることは可能ですが)までが実用的な限界なのです。
そこで、1970年代に当時ハンガリーのMezeiが提案した波長分解能とエネルギー分解能を分離する画期的な方法が、ここで説明する「中性子スピンエコー法」なのです。
強度を落とさずにエネルギー分解能を上げるにはどうしたらよいか。それには、波長分解能とエネルギー分解能を分離する必要があります。そのために、NSEでは磁場中での中性子スピンの歳差運動を利用します。

例えばコマが地上で(すなわち重力場の中で)回っている時には首振り運動する様子が見られますが、この現象(歳差運動)は外場中の自転運動としては一般的なもので、同様に中性子スピンも磁場中で歳差運動を行います。(これをLarmor precessionと呼びます。)この回転の角速度ωLは、
ωL=-4πγnμNB/h (γn、μNはそれぞれ定数)
と記述できます。すなわちこの首振り運動の速さは、スピンと磁場との間の角度や中性子の速度によらず、磁場の強さBのみで決まることになります。
そこで入射する中性子のスピンを揃えておいて、試料に当てる前と後に磁場を置きます。すると遅い中性子は磁場中に滞在する時間が長いので大きく回転するのに対して、速い中性子はあまり回転しない、と言うことになります。そして試料の前後でこの歳差運動を逆に回転させることにすれば、最後には中性子の速度によらずにすべてのスピンが揃うことになります。これを「スピンエコー収束」と言います。
|
|
||
|
もし試料で非弾性散乱が起きて中性子の速度が変わると、その中性子は第二歳差磁場コイルを出たところで元の角度には戻れなくなります。つまりその場合は「エコーが崩れる」わけです。従ってアナライザで中性子の偏極率を測定して完全弾性散乱の場合に比べてどれだけ落ちたか(すなわち、元に戻らなかったスピンがどれだけあったか)を調べれば、散乱中性子に非弾性散乱がどれだけ含まれるかを非常に精度良く調べることができるわけです。従って、速い中性子と遅い中性子を同時に使って(つまり強度を落とすことなく)その速度変化を正確に調べることができるのです。
※なお、実際には2つのコイルの間でスピンの向きを180゜回すことで、第一歳差磁場コイルと第二歳差磁場コイルの磁場の方向を同じにして実質的に逆回転になるようにしています。
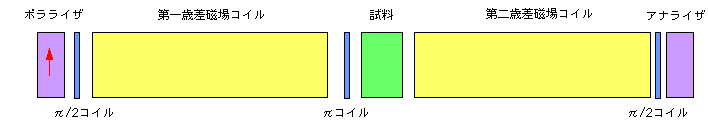
またポラライザの後、アナライザの前には90゜回転させるコイルも置いてあるので、実際には中性子スピンは次のような動きをしています。
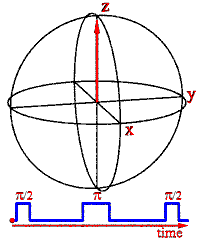 (なおこの図はHMIのホームページより拝借しました。)
(なおこの図はHMIのホームページより拝借しました。)