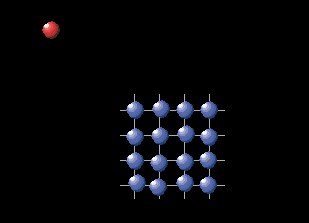
NSEの基礎
1.1 中性子散乱とは
1.2 中性子非弾性散乱
2.1 中性子スピンエコーの特徴
2.2 中性子スピンエコーの原理
3.1 NSEの装置
3.2 世界のNSE分光器
4.1 NSEデータの意味
4.2 NSEデータの解析
「中性子」とは陽子とともに原子核を構成する素粒子の一種です。すべての素粒子は「粒子性」と「波動性」を持ちますので、中性子も粒子としての性質と波としての性質を持っています。
|
中性子の粒子としての性質 |
||||||||
|
量子力学によると、これら素粒子の波としての性質は E=kBT=(1/2)mv2=h2/(2mλ2) によって記述できます(ここでkB,hはそれぞれボルツマン定数とプランク定数)。従って低温における中性子(いわゆる冷中性子)、室温付近における中性子(熱中性子)、更に高温の中性子(熱外中性子)のエネルギーと波長との関係は、次のようになります。
|
中性子の波としての性質 |
||||||||||||||||
|
つまり、室温付近の中性子を取り出せばちょうど結晶格子の間隔程度の波長となるわけです。従ってX線や電子線のように結晶により回折するので、物質のミクロな構造を調べるために使えるのです。
ここで重要なことは、この熱中性子のエネルギー領域(5-100 meV)がちょうど結晶格子の振動エネルギーと同程度だ、と言うことです。中性子がこれら運動状態にある結晶中の原子に当たると、運動量保存則とエネルギー保存則に従って速度が速くなったり遅くなったりします。
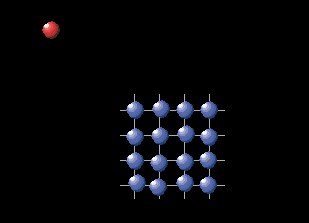
エネルギーのやり取りをしない散乱を「弾性散乱」、やり取りする散乱を「非弾性散乱」と言い、非弾性散乱のうちわずかなエネルギーのやり取りしかしない散乱を特に「準弾性散乱」と呼びます。中性子散乱がX線や電子線に比べて有利な点はいろいろある(磁気構造が見れるとか、同位元素効果があるとか)のですが、特に重要なのがこの「非弾性散乱」を用いて対象となる系の運動状態を見ることができる事だ、と言えます。
物質の運動状態を調べる様々な実験方法のうち、特に中性子非弾性散乱が優れているのは空間的な構造と運動(エネルギー遷移)の状態についての情報を同時に測定できる、と言うところにあります。
この図は空間的な構造のスケールを逆格子ベクトルQで、またエネルギー遷移の量をΔEで書いたもので、様々な実験方法がカバーする領域を模式的に示しています。この中で色付きで示したのが中性子散乱による方法です。空間スケールとしてはちょうど結晶の格子定数や原子間隔の大きさである1Å-1付近からウィルスなど生命体の最小の大きさである数千Åまで、またエネルギースケールではこれらの特徴的な励起エネルギーである数neV〜数eV程度の範囲をカバーしています。すなわち、物質の構造と運動状態を総合的に明らかにする上で、最も強力な実験方法だと言って良いでしょう。
それでは、この中性子非弾性散乱はどのように測定するのか。一言で言えば試料となる物質に中性子ビームを当て、その時のエネルギーのやり取りにより中性子速度の変化(速度が変化すれば当然波長も変化する)を測定するのですが、その方法には大きく分けて3つあります。
これらの実験方法にはそれぞれ得意とするQレンジやエネルギー遷移のレンジがあるため、試料に応じて、あるいは狙うサイエンスに応じて使い分けることになります。