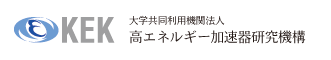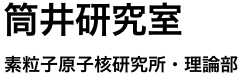| 日時: | 2013-12-17 15:00 - 16:00 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | コライダー実験における崩壊粒子の運動量エンタングルメントを用いたベル不等式検証 |
| 講演者: | 陳 詩遠 Shion Chen (University of Tokyo) |
| 概要: | ベルの不等式は 2 粒子間の相関について、古典論が満たすべき上限を与える
式である。量子論の下では、 エンタングル状態など特定の条件下で不等式が破
れることが知られており、いわば古典論と量子論の判別式のようなものである。
これまで既に多数の光学実験において破れが報告され、量子論の「勝利」はほぼ
確定したが、フェルミオンや質量のある粒子系での実験例は依然として少ない。
しかし量子力学の普遍性検証という観点において、また一般に重い粒子は古典性
が強いという点で、これらの系での検証は非常に興味深い。また、未だよく理解
されてない量子力学の非局所性などの性質を探る上でも重要である。
高エネルギーコライダー実験で生成される不安定粒子は、その崩壊で様々なエン タングル状態を生じるため、これらの検証手段として有望である。 我々は今回 チャーモニウム崩壊J/ψ, ηc, χc0→ΛΛ→pπpπに主に着目した。チャーモニウムから 崩壊したΛΛのペアはヘリシティー・エンタングル状態を形成する。ΛΛ対は続けて 弱崩壊Λ→pπ-, Λbar→pbar π+を行うが、この崩壊では崩壊角分布が親粒子の偏極 の方向と相関を持つ。従って終状態のπ+π-は親粒子の性質を引き継いで互いの運 動量がエンタングルし、量子論では2つπの方向が古典論の予言を超えた大きな相 関を予想する。この性質を用いたベル不等式および量子力学の検証は1980年代に 提案されたが、BES実験などのチャームファクトリーの登場により近年になって 理論・実験双方からのアプローチが盛んになってきた。 今回講演ではこれらに 関する近年のアクティビティや、我々が行った新しいベルの不等式検証の定式化 および実験可能性について論ずる。さらに同様の崩壊構造を持つZ→ττ→πνπν、H→τ τ→πνπνに関しても検討し、超高エネルギー実験における量子力学基礎実験のポテ ンシャルについても考えてみようと思う。(これはHiggs bosonを応用する初の 試みである!) |
| 日時: | 2013-11-20 15:30 - 16:30 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | 弱測定増幅の統計的限界 |
| 講演者: | 田中 咲 Saki Tanaka (Keio University) |
| 概要: | Aharonov, Albert and Vaidmanが提唱した弱測定法は、スピン1/2粒子のスピンを測定した結果として100を与える測定であった。 この測定の結果は弱値とよばれ、事前選択状態と事後選択状態に依存する。 弱値は、事後選択状態が事前選択状態に近づくとき、無限に大きな値を取る。 この性質を用いて、弱測定は増幅技術として用いられてきた。 しかし、事後選択は確率的な操作であり、事後状態の生成は運任せである。 我々はこの事後選択の失敗について考慮し、推定論の立場から信号増幅法の評価を行った。 結果、我々は事後選択を必要とする弱測定による信号増幅には限界があることを示した。 本セミナーでは、弱測定と数理統計に関する議論を行ったうえで、我々の結果について説明する。 |
| 日時: | 2013-07-29 14:00 - 15:00 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | Complex probabilities as fundamental law of physics: What weak measurement statistics tell us about the nature of reality |
| 講演者: | Prof. Holger F. Hofmann (Hiroshima University) |
| 概要: | According to quantum mechanics, the measurement of a property A
necessarily disturbs the system, so that the value of a different
property B obtained after the measurement of A is different from the
value of B before the measurement of A. However, it is possible to
decrease the measurement interaction to the point where the disturbance
of B is negligible. In this weak measurement limit, it is possible to
determine the value of A conditioned by the final measurement outcome of
B, without disturbing B in the process. The weak values obtained in such
measurements have attracted a lot of attention because they can exceed
the limits set by the extremal eigenvalues of A [1]. Recently, it has
been shown that weak values can be described as averages of complex
valued probability distributions, where the possibility of negative real
parts not only explains the observation of averages outside the range of
eigenvalues, but also resolves a number of quantum paradoxes, which are
usually based on the assumption of positive joint probabilities [2].
In this presentation, I show that complex conditional probabilities provide a consistent explanation of all quantum effects. In particular, it is pointed out that complex conditional probabilities describe universal relations between three physical properties that represent the correct quantum limit of classical determinism. In these relations, the complex phase corresponds to the action of transformations between two physical properties along the third. Importantly, a simultaneous assignment of realities to the three different properties is impossible, because measurement interactions change the effective reality of the system according to the laws of dynamics. This relation between complex probabilities and measurement dynamics can be summarized by a quantitative relation which I call the law of quantum ergodicity. As I recently showed, this law can be used to derive the complete Hilbert space formalism, providing a physical explanation of quantum mechanics in terms of the fundamental relation between the reality of physical properties and the dynamics by which they are observed [3]. The results recently obtained from weak measurements of quantum systems might thus be the key that unlocks the mysteries of quantum mechanics. [1] Aharonov et al., PRL 60, 1351 (1988) [2] Hofmann, NJP 14, 043031 (2012) [3] Hofmann, arXiv:1306.2993 |
| 日時: | 2013-07-17 14:00 - 15:00 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | Detectors for probing relativistic quantum physics beyond perturbation theory |
| 講演者: | Eduardo Martin-Martinez (Institute For Quantum Computing, University of Waterloo) |
| 概要: | We develop a general formalism for a non-perturbative treatment of harmonic-oscillator particle detectors
in relativistic quantum field theory using continuous-variables techniques. By means of this we forgo
perturbation theory altogether and reduce the complete dynamics to a readily solvable set of first-order,
linear differential equations. The formalism applies unchanged to a wide variety of physical setups,
including arbitrary detector trajectories, any number of detectors, arbitrary time-dependent quadratic couplings,
arbitrary Gaussian initial states, and a variety of background spacetimes. As a first set of concrete results,
we prove non-perturbatively--and without invoking Bogoliubov transformations--that an accelerated detector
in a cavity evolves to a state that is very nearly thermal with a temperature proportional to its acceleration,
allowing us to discuss the universality of the Unruh effect. Additionally we quantitatively analyze the problems of
considering single-mode approximations in cavity field theory and show the emergence of causal behaviour
when we include a sufficiently large number of field modes in the analysis. Finally, we analyze how the
harmonic particle detector can harvest entanglement from the vacuum. We also study the effect of noise
in time dependent problems introduced by suddenly switching on the interaction versus ramping it up slowly
(adiabatic activation).
Ref. Phys. Rev. D 87, 084062 (2013) |
| 日時: | 2013-07-05 15:00 - 16:00 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | 重力波観測における標準量子限界について |
| 講演者: | 佐々木 寿彦 Toshihiko Sasaki (Photon Science Center, University of Tokyo) |
| 概要: | 干渉系型の重力波観測装置においては、当初、標準量子限界と言われる量子力学 の不確定性による検出限界が存在すると言われていた。 これがそうではないということを小澤の不等式が示していると一般に考えられて いるが、実際の対応関係が具体的に語られることは少ない。 本発表では、具体的な測定装置における標準量子限界の回避方法をレビューし、 両者を比較する。 |
| 日時: | 2013-06-28 15:30 - 16:30 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | エンタングルメントからの熱力学的仕事のゲイン |
| 講演者: | 布能 謙 Ken Funo (University of Tokyo) |
| 概要: | マクスウェルの悪魔は量子情報、熱力学、(非平衡)統計力学などの分野で長い間活発に議論されてきた。マクスウェルの悪魔はシステムのミクロな自由度を測定し、
その測定結果に応じてシステムをフィードバックすることができる。そのため、マクロな自由度のみを操作するような場合よりもシステムをより操作することができるため、熱力学第二法則を超えて仕事を取り出すことが示唆される。
測定とフィードバック制御下での一般化された第二法則は沙川と上田によって示され、第二法則を超えて取り出せる仕事はシステムと測定結果を蓄えるメモリーとの間の相関を表す量子‐古典相互情報量によって特徴づけられることが示された [1]。
また、フィードバックによってシステムが得をした仕事の分だけメモリーに仕事を注入しなければいけないことも示され、全体としては第二法則に矛盾しないことが示された [2]。今回の発表では二つのシステムの間にエンタングルメントがある場合を考え、
この相関をフィードバック制御することで取り出せる仕事について議論する [3]。取り出せる仕事は二つのシステムとメモリーの間の三体間の相関で特徴づけられ、初期にあったエンタングルメントについてメモリーがどれだけアクセスできるかによって決まることが明らかになった。
[1] T. Sagawa and M. Ueda, Phys. Rev. Lett. 100, 080403 (2008). [2] T. Sagawa and M. Ueda, Phys. Rev. Lett. 102, 250602 (2009). [3] K. Funo, Y. Watanabe and M. Ueda, arXiv:1207.6872 (2012). |
| 日時: | 2013-06-14 14:00 - 15:30 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | 19世紀末から20世紀初頭のウィーンの物理 |
| 講演者: | Wolfgang Bentz (Tokai University) |
| 概要: | 19世紀末から20世紀初頭にウィーンで生まれもしくはウィーンで活躍 した物理学者は例えば L. Boltzmann, V. Hess, E. Schrodinger, W. Pauli. L. Meitner など有名な例が多いです。その物理学者の記念と なるところおよび町の雰囲気をこのセミナールで紹介したいと思います。 特に Boltzmann と Schrodinger の生涯を取り上げ、模範的な考え方 と生き方などについて皆さんと一緒に考えて見たいと思います。 |
| 日時: | 2013-06-14 11:00 - 12:00 |
| 場所: | 研究本館 1階 会議室3 |
| 題目: | 量子演算子の弱値展開:量子測定による歴史の消去への応用 |
| 講演者: | 全 卓樹 Taksu Cheon (Kochi University of Technology) |
| 概要: | ここ四半世紀、アハロノフの弱値 weak value という妖怪が、量子論界隈を徘徊してやむ事がなかった。 「弱い測定 weak measurement」による実験的実現も得る一方、 数多くの論文の中で時に神秘的な装いで現れるこの弱値概念であるが、 しかしこれを 通常の量子力学の形式の中でどう理解すればいいのか、多くの研究家が頭を悩ませてきたのも事実である。 今回の話では、この量子的弱値を、ヒルベルト空間の直交系を用いたごく普通の量子論の定式化の枠組みに、どう位置づけるかを考えてみたい。 ここで鍵となるのが「量子演算子を完全に記述する弱値の一式」という考え方である。 さらにそのような一式を持ち出す利点を、 「射影測定を行う時どのような場合に歴史を消せるか」という応用問題を取り上げて説明してみたい。 |
| 日時: | 2013-05-10 16:00 - 17:30 |
| 場所: | 研究本館 3階 セミナー室322 |
| 題目: | 日本における量子物理学研究の始まりと量子力学の解釈 |
| 講演者: | 伊藤 憲二 Kenji Ito (The Graduate University for Advanced Studies) |
| 概要: | 日本の物理学は量子力学の導入を契機に、1930年代に国際的な研究水準に達した。 本セミナーでは、この時期の日本の物理学研究がどのように変化をし、日本で量子物理学の研究が始まったのかについてお話する。 とくに、その過程で、量子力学の概念的な側面、不確定性関係、相補性、波動関数の確率解釈等に対して、 日本の物理学者やその他の知識人がどのように反応し、どのような議論が生じたのかについて述べる。 |
KEK理論部セミナー